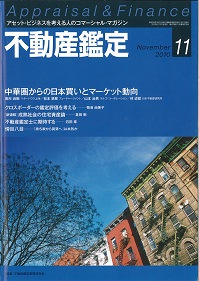


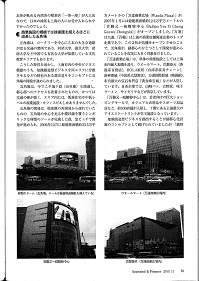
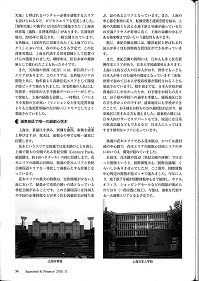
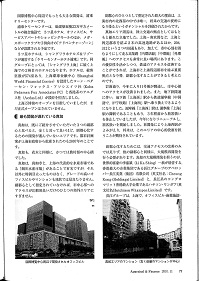
 芝田 優巳(しばた ゆうじ)
芝田 優巳(しばた ゆうじ)
㈱シノケングループ 経営企画部 海外事業室 課長。
不動産鑑定士、税理士。上海在任歴4年。
早稲田大学大学院商学研究科修了。
野村不動産㈱でオフィスリーシング、都市開発コンサルティングなど、あおぞら銀行(旧日本債権信用銀行)で不動産鑑定評価、不動産投資分析、企業財務分析などを行った後、2006年から上海で中国不動産ビジネスに関わる。
中国では、不動産コンサルティング会社で不動産市場調査、鑑定評価、不動産投資コンサルティング業務、JVのアレンジメントなどを経験。昨年、㈱シノケングループに入社し、中国不動産投資コンサルティングなどを行う一方、中国人向け日本不動産投資コンサルティング業務も行うなど、現在は、日中両国の不動産ビジネスに携わっている。(記事に関するお問い合わせ、感想、取り上げて欲しい話題、中国ビジネスに関するお問い合わせなど、 y-shibata@shinoken.co.jp までご自由にご連絡ください)
上海通信11月号記事
上海発展のカギを握る副都心計画
上海市の副都心構想
上海市は、あくまでも「市」であるため、日本の感覚では、たいして大きくないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、中国でいう「市」は、日本の都道府県にあたります。上海の面積は6,340平方キロメートルで東京の約2.6倍、人口は約2,000万人です。東京の人口は約1,300万人ですから、上海は、人口でも東京を大きく上回ります。
上海の人口分布図を見ると、中心部に偏っており、都市機能を分散させると共に、人口を郊外に分散させるという政策が採られています。
上海市全体都市計画(1999年~2020年)でも、上海市政府がある人民広場(地名です)を中心に、4つの副都心を建設する構想が盛り込まれています。
4つの副都心は、上海のへそとも言える人民広場を中心に、ほぼ四方に分布します。
副都心は、徐家匯(人民広場の南西)、五角場(人民広場の北東)、浦東花木(人民広場の南東)、真如(人民広場の北西)の4つです。
それぞれの計画規模は、徐家匯が約2.2平方キロメートル、五角場が約2.2平方キロメートル、浦東花木が約2.0平方キロメートル、真如が約1.6平方キロメートルです。
4つのエリアは、計画の発表前は、単なる上海の郊外でしかありませんでした。
今回は、今後の上海発展のカギを握るとも言える、4つの副都心についてご紹介させていただきたいと思います。
副都心として最初に開発が進んだ徐家匯
徐家匯は、『トータルサービスの行き届いた、現代都市』というコンセプトの下、4つの副都心の中で最も早く再開発が進められました。現在では、上海市の交通の中枢エリアにもなり、上海の渋谷とも言われるほどに発展し、学生や若い夫婦などを中心に大変な賑わいを見せています。
徐家匯は、90年代までは、低層住宅が密集するエリアでしかなく、上海交通大学(中国有数の名門校)や徐家匯天主堂などのほか目立つ建物はありませんでしたが、現在では、上海を代表する「太平洋百貨」「東方商廈」「美羅城(Metro City)」「港匯広場」「匯金広場」など有名百貨店が集積し、グレードの高いオフィスビル、五ツ星ホテル、娯楽施設、コンピューターショップなどが建てられ、上海有数の繁華街へと変貌を遂げました。
変貌を遂げた徐家匯の象徴とも言えるのが、ハイグレードオフィス「港匯広場(Grand Gateway)」です。
「港匯広場」は、香港系大手デベロッパーである恒隆集団(Hang Lung Group Ltd.)が建設したものです。
恒隆集団は、上海で最も有名なオフィスビルのひとつで、高級ショッピングロード南京西路のランドマーク的な建物である「恒隆広場(Plaza66)」を建設したデベロッパーです。恒隆集団が副都心計画に加わったことが、徐家匯をここまで成長させた要因のひとつになっているとも言えると思います。
徐家匯エリアには、大学生や外国人留学生のほか、日本人をはじめ多くの外資系企業の駐在員が住んでおり、現地の日本人にもなじみの深いエリアになっています。
前述した美羅城の地下1階に、既存の商業施設をリニューアルし,日系のショップを集めた「五番街」が今年の8月にオープンしました。日系以外のショップもありますが、「無印良品」、雑貨店「フランフラン」、ベーカリー「ドンク」、抹茶カフェ「ナナズ・グリーンティーカフェ」、ドラッグストア「セガミ」、下着専門店「ピーチ・ジョン」、ソフトクリームスタンド「神戸六甲牧場」、「日比谷花壇」、など、日系のショップも多く入居しています。
テナントには、中国初進出の日系ショップも多いのが特徴です。徐家匯は、既に成熟し、上海を代表するエリアとなっており、テナントから見れば、初進出するなら出店して間違いのないエリアとして認識されているのでしょう。
弊社の顧客の中にも「五番街」に出店したいという方が何社かいらっしゃり、オーナー(デベロッパー)とも交渉しましたが、オーナーは、非常に強気でした。というのは、美羅城は、非常に人気のある商業施設で、既存入居テナントのうちピザハットやスターバックスは美羅城店が世界で最も売上が高い店舗となっていると言われるほど集客力があるからです。オーナーサイドは、初進出よりも実績のあるテナントを求めていたため、今回中国へ初進出を果たした店舗はオーナーとの交渉は大変だったことと思います。こういうケースでは、要求される賃料も高くなりがちですが、上海で最初からこのような一等地に進出できるチャンスは非常に稀であり、かつ、1店舗目の店舗が美羅城にあることをアピールすることで2店舗目を他のエリアに出店するときの出店交渉が容易になる、という事情を理解して高い賃料を払う決断ができるかどうかが入居できるかどうかの最大のポイントになります。
先日も五番街に行きましたが、入居店舗のうちでは、「ナナズ・グリーンティーカフェ」に行列ができており、特に客が多かったのが印象的でした。同社は、「抹茶」という切り口から、誇りある日本の食文化や伝統を「日本のカフェ」として世代や国を超えて多くの人々に発信し続ける ― と考えられているようです。ここ中国ではお茶好きの人が多く、数十種類のお茶が飲める台湾系の喫茶店「一茶一座」が大人気なので、日本の抹茶も上海の人には受け入れられやすかったのでしょう。
商業施設の規模では徐家匯を超えるほどに成長した五角場
五角場は、ロータリーを中心に5本の大きな道路が走る交通の要所であり、同済大学、復旦大学、財経大学など中国でも有名な大学が集積している文化教育エリアでもあります。
こうした特性を活かし、上海市内の中央ビジネス機能のうち、知識創造型ビジネスを同エリアに分散させるなどの特色のある都市造りをコンセプトに五角場の開発が進められました。
五角場は、今でこそ地下鉄(10号線)も開通し、都心部へのアクセスも改善されたものの、かつては交通の便が悪く、エリア内には、低層住宅や中低レベルの商業施設・オフィスビルしかありませんでした。
五角場の開発は、徐家匯の再開発から遅れていたものの、五角場の中心を走る中環状線を覆うシンボリックな卵型のドームが完成した後、急ピッチで開発が進められ、2006年12月に総建築面積約33.5万平方メートルの「万達商業広場(Wanda Plaza)」が、2007年1月には総建築面積約12.6万平方メートルの「百聯又一城購物中心(Bailian You Yi Cheng Gouwu Zhongxin)」がオープンしました。「万達」は大連、「百聯」は上海の商業店舗関連企業のトップ企業であり、この2社が店舗をオープンさせたことで、五角場が、副都心のひとつとして開発が進められていることを市民に大きく印象付けました。
「万達商業広場」は、単体の商業施設としては上海市内最大規模を誇り、ウオールマート、巴黎春天(香港系百貨店)、HOLA家居(台湾系家具チェーン)、新華書城(中国系大型書店)、万達国際影城(映画館)、市内最大の宝石専門店「黄金珠宝城」などが入居しています。日系企業では、山崎パン、吉野家、味千ラーメン、サイゼリヤなどが出店しています。
「百聯又一城購物中心」は、若者向けの巨大ショッピングモールで、カジュアル衣料品やスポーツ用品店など、約500店舗が入居し、7階にある上海最大のアイススケートリンクが目玉施設となっています。
知識創造型ビジネスを創出することが副都心化計画のコンセプトとして掲げられていましたが、「創智天地」と呼ばれるベンチャー企業を誘致するエリアも設けられるなど、ビジネスエリアも充実しました。「創智天地」の裏手には1935年に建築された「上海市体育場(通称:江湾体育場)」があります。江湾体育場は、2005年に復元され、一般公開されています。五角場は、1930年代に計画された「大上海プロジェクト」においては、市の中心となる予定で、この江湾体育場は、上海を代表する体育設備として位置づけられ建築されました。戦時中は、旧日本軍の爆弾庫として使われたこともあったそうです。
また、五角場の背後(北方)には、新江湾というエリアがあります。このエリアは、五角場エリアの開発と共に、数年前より高級住宅エリアとして開発が急ピッチで進められました。住宅用地の入札には、外資系・中国系の大手不動産デベロッパーがこぞって参加し、土地の価格も急騰し、一時期は、「パンより小麦粉の方が高い(マンションなど住宅売買単価よりも土地売買単価の方が高い)」エリアとしてよく報道されていました。
浦東地区で唯一の副都心花木
上海は、黄浦江を挟み、西側を浦西、東側を浦東と呼びますが、花木は、副都心の中では唯一浦東に位置します。
花木というエリアは狭義では花木鎮のことを指し、上海で最大の公園である世紀公園(Century Park。総面積は、約140ヘクタール)の南に位置します。花木エリアの副都心計画は、狭義の花木エリアと世紀公園周辺エリアを一体化して副都心とする計画となっています。
花木エリアの最大の特徴は、自然環境が少ない上海において、緑豊かで市民の憩いの場となっている世紀公園があることです。この公園周辺には外国人や中国の企業幹部などが多く住む高級住宅が建ち並ぶ、品のあるエリアとなっています。また、上海の中心部を東西に走り、虹橋空港と浦東空港を結ぶ、上海の大動脈とも言える地下鉄2号線が通っているため交通アクセスが非常に良く、上海の金融の中心である陸家嘴まで近いという優位性もあります。
既に、世紀公園北側には、聯洋地区と呼ばれる外国人が多く住む国際的な居住区ができあがっています。
また、世紀公園の西側には、日本人も多く住む新興住宅エリアがあり、日本人学校浦東校もあります。上海には約5万人の日本人がおり、世界でもっとも日本人が多く住む海外の都市となっています(来春、世界で初めて日本人学校高校部が開校されることも発表されています)。数年前までは、日本人学校が浦西地区にしかなかったため、お子様をお持ちの方々は、お子様の学校への通学を考慮し、浦西地区に住む方も多かったのですが、浦東地区にも学校ができたことで、お子様をお持ちの方の選択肢が広がり、浦東地区に住まれる方も増えました。浦東校の隣には、日本人向けサービスアパートもでき、周辺には日系の飲食店舗などもできるなど、日本人にとってはますます便利なエリアになっています。
狭義の花木エリアである花木鎮は、かつては農村部の中心鎮で、花木エリアの副都心計画エリアの中においては、開発が遅れていました。
以前は、花木鎮の周辺(世紀公園の南側)で目立った建物というと、国際博覧中心(国際会議場)くらいしかありませんでしたが、ここ数年、国際博覧中心周辺の開発が急ピッチで進みました。今年に入り、地下鉄7号線が国際博覧中心まで延伸し、ホテル、オフィス、ショッピングモールなどの開発が進められており(一部は既に竣工)、今後は、浦東を代表する一大商業エリアとなる予定です。
国際博覧中心周辺でもっとも大きな開発は、浦東ケリーセンターです。
浦東ケリーセンターは、総建築面積23万平方メートルの複合施設で、5ツ星ホテル、オフィスビル、サービスアパートやショッピングモールのほか、メガ・スポーツクラブや子供向けの「アドベンチャーゾーン」などが設置される予定です。
5ツ星ホテルは、シャングリラホテルズ&リゾーツが運営する「ケリーセンターホテル浦東」です。同グループにとっては、「シャングリラ上海」に続く上海での2軒目のホテルになります。ホテルは、総客室数が574室あり、上海環球金融中心(Shanghai World FinancialCenter)を設計したコーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツ社(Kohn Pedersen Fox Associates PC)と香港系のアエダス社(AedasLtd.)が設計を担当しました。
上海万博前のオープンを目指していましたが、まだ正式オープンはされていません。
最も開発が遅れている真如
真如は、既にご紹介させていただいた3つの副都心と比べると、全くと言って良いほど、副都心化するための開発が進んでいないエリアです。都市計画案が上海市政府から批准されたのも2007年のことです。
真如も、花木と同様に、かつては農村部の中心鎮でした。
真如は、真如寺と、上海の代表的な水産市場である「銅川水産市場」があることで有名ですが、それ以外に特別目立ったものはなく、グレードの高いオフィスビルやマンションも現状では見当たりません。副都心として指定されていなければ、市中心部へのアクセスが比較的良いだけのひとつの郊外エリアにすぎません。
副都心のひとつとして指定された最大の理由は、上海市内の北西部の中では唯一、将来の交通の要所になり得るというポテンシャルを評価されたからです。
真如エリア周辺は、陸上交通の拠点としてはもともと優れた立地でした。上海-南京間など、上海と周辺都市を結ぶ2本の高速道路があるほか、204、312という2つの国道もあり、加えて、市中心部を囲むようにして走る高架路「内環状線」「中環線」「外環線」へのアクセスも非常に良い場所にあります。この優位性を活かしつつ、鉄道のアクセスを改善することができれば、上海市と上海周辺都市を結ぶ重要拠点となり得、副都心化することができると考えたのです。
計画通り、今年に入り11号線が開通し、市中心部へのアクセスが改善されました。また、地下鉄開通に伴い、地下鉄「上海西」駅から鉄道滬寧線(中国語で、沪宁铁路)「上海西」駅へ乗り換えできるようになりました。滬寧線「上海西」駅は、滬寧線「上海」駅の隣駅であることもあり、3年程前から旅客扱いを休止していましたが、今年になりリニューアルし、旅客扱いを開始しました。再開発により上海西駅がよみがえり、将来は、このエリアの中心的役割を担うことが期待されています。
副都心化するためには、交通アクセスの改善のみでは足りず、他の副都心と同様に、大規模再開発を行う必要があります。真如の大規模開発を担うのが、世界的富豪の李嘉誠(Li Ka Shing)一族が経営する、香港最大の企業集団である長江グループのデベロッパー長江実業(集団)有限公司(英文社名:Cheung Kong (Holdings) Limited)と、長江系のコングロマリット香港最大手企業であるハチソン・ワンポア(英文社名:Hutchison Whampoa Limited)です。
長江グループは、上海で、オフィスビル・商業施設・ビラなど様々な用途で大規模開発を行っていますが、真如での開発は、グループにとっても最大級の開発となります。
長江グループが真如で予定している開発の総建築面積は約114万平方メートルで、300メートル級のオフィスビルを中心に、五ツ星ホテルや住宅など100~150メートルの建物が付近一帯に建てられる計画となっています。全てが竣工するのは2018年を予定しているため、真如が、他の3つの副都心と並んで、名実共に副都心となるにはまだ時間がかかりそうです。
都市計画によれば、他に、真如エリアのシンボルとも言える真如寺は保存されること、銅川水産市場が移転することなどが決まっています。
真如エリアの不動産は、市内の中心部から同距離に位置する他のエリアと比較すると割安感があります。加えて、副都心化計画があり、真如エリアの潜在力は大きいことは明らかであると言って、真如エリアの不動産投資を薦める記事、広告をよく目にしますが、これまでのところ副都心としての開発が進むからという理由で価格が上昇するという明確な動きはありません。しかしながら、開発が進むにつれ、真如エリアの都市力が増し、不動産の市場価値が上がるのはほぼ間違いないのではないかと思われます。
11号線が開通したことにより、「真如」駅の先(嘉定区)も、市中心部への通勤圏内となったため、マンション開発が活発になってきています。前述したように、地下鉄10号線の開通と五角場の副都心化に伴う再開発により、五角場の先にある新江湾というエリアのマンション価格が高騰しましたが、真如の先にある嘉定区のマンション価格がどう推移していくのかも注目に値するところです。
上海の4つの副都心は、それぞれが個性を持ち発展していますが、上海がより発展していくうえで、4つの副都心がそれぞれの役割を果たすことが不可欠であると思えます。4つの副都心が機能すれば、市内中心部と副都心、郊外とが有効に結び付けられ、都市としての厚みを増していくことと思われます。
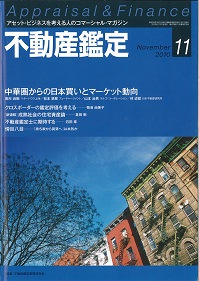


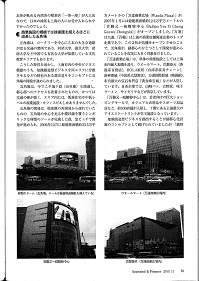
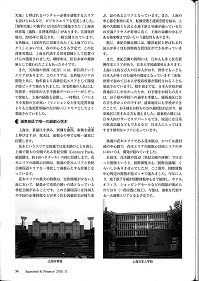
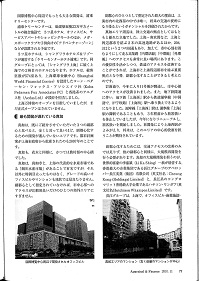
 芝田 優巳(しばた ゆうじ)
芝田 優巳(しばた ゆうじ)